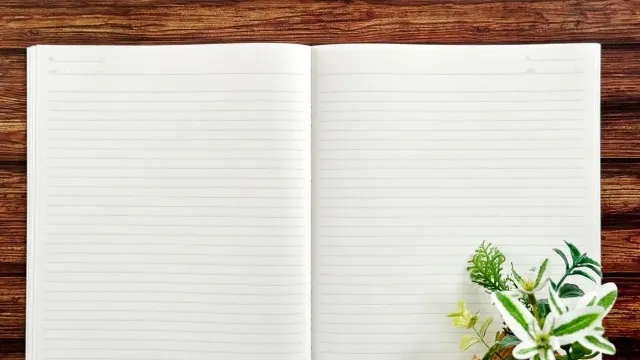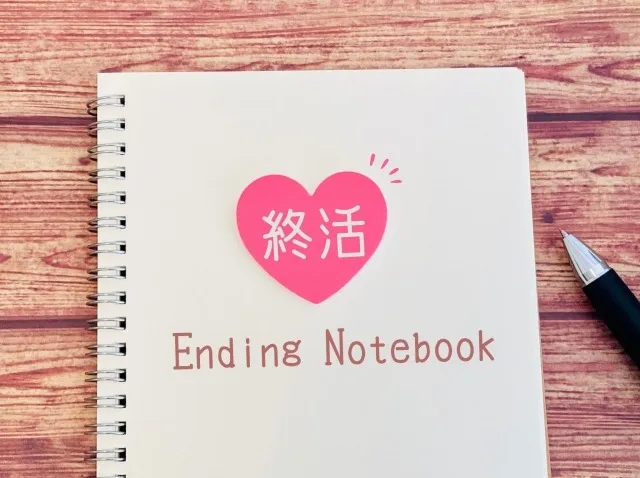任意後見人とは?任意後見制度の仕組みや任意後見監督人との違いを紹介
2025/03/20
老後の不安として、認知能力や判断力の低下を挙げる方も多いのではないでしょうか。
認知症などで身の回りのことが決められなくなったり、他人に迷惑をかけたりしたくないとお考えの方は、「任意後見制度」を検討するのがおすすめです。
任意後見制度を利用するには、認知症などになった時に代わりに契約や財産管理などを行う「任意後見人」を決める必要があります。
任意後見人とはどのような人がなれるのか、身近に頼める人がいないときはどうすればいいのかを解説します。
任意後見人と似ている「任意後見監督人」との違いも説明するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
任意後見人とは
任意後見人とは、任意後見制度を利用して自分の代わりに判断や手続きなどを代わりに行う人を指します。
そもそも任意後見制度とは何なのか、任意後見人の詳細とあわせて解説します。
任意後見制度の仕組み
任意後見人について理解するために、まずは任意後見制度の仕組みを見ていきましょう。
任意後見制度は、あらかじめ任意後見人になる人を決めておき、認知症や障害などの理由で判断することが難しくなったと感じたときに、自分の代わりに任意後見人が手続きや契約などを行う仕組みです。
■任意後見制度の流れ
|
任意後見制度は任意後見契約書を公証役場で公正証書にするため、法的執行力を持つ公の契約です。
任意後見制度を利用するには、以下の3つの役割をもつ人が重要になります。
■任意後見制度で重要な役割
|
名称が似ているのでややこしいですが、任意後見制度を理解するうえで大切なポイントなので詳しく掘り下げていきます。
任意後見受任者
「任意後見受任者」は、将来的に任意後見人になる人です。
任意後見契約を結ぶ時点ではご本人に判断力があり、まだ任意後見制度を利用する段階ではないので、将来的に任意後見人になる予定の人もこの段階では権限を持ちません。
結果的に、任意後見人になる予定の方は契約締結の際はまだ、任意後見受任者と呼ばれます。
任意後見監督人
任意後見契約の効力が発生するタイミングは、以下の要素がすべて揃ったときです。
■任意後見契約の効力が発生するタイミング
|
任意後見制度を実際に利用する際は、ご本人の行動に不安が出てきたことだけでなく、家庭裁判所に家族などが申し立てて「任意後見監督人」を決めてもらう必要があります。
任意後見監督人とは、任意後見受任者が任意後見人となった際に、任意後見契約に従って適切なサポートを行っているかを監督する人を指します。
任意後見契約は任意後見監督人と任意後見人の両方が揃って初めて、効力を発揮するのです。
任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、ご本人やご家族とはまったく関係のない人が選ばれます。
任意後見人
任意後見監督人が決まったら、任意後見受任者は「任意後見人」となります。
任意後見監督人の指導の下、契約に沿った内容で手続きや支援などを開始します。
任意後見人は依頼したい本人が決めるのが原則
任意後見制度の特徴は、将来に不安を感じているご本人が自分で制度の利用を決め、判断力があるうちに任意後見人(任意後見受任者)を指名できる点です。
任意後見契約は自分の代わりに大切な契約や財産の管理を頼むので、信頼できる人にお願いしたいと考えるのは当然のことです。
配偶者や子ども、親戚はもちろん、友だちや婚姻関係のないパートナーでも任意後見人になれます。
また、身近に任意後見人を委任できる人がいない場合は、司法書士や弁護士などの専門職や社会福祉団体に依頼もできます。
条件によっては任意後見人になれない人もいる
任意後見人は、ご本人が依頼したいと決めた人なら基本的に誰でもなれますが、以下の条件に当てはまる場合は資格がありません。
■任意後見人になれない人の条件
|
ご本人のお子さんであっても、未成年者は任意後見人になれず、成人でも家庭裁判所から適切でないと判断された場合は対象から外す必要があります。
法定後見制度は家庭裁判所が後見人を決める
任意後見制度と似ているものに「法定後見制度」がありますが、どちらも「成年後見制度」の一つです。
ただし、法定後見制度はすでに判断力や認知力が低下している人に対して、家庭裁判所が必要に応じた後見人を決める仕組みです。
つまり、任意後見制度はご本人が自分で後見人を決め、法定後見制度は家庭裁判所が後見人を決める点に大きな違いがあります。
任意後見人になる上での注意点
任意後見人になる場合は、以下の点に注意が必要です。
■任意後見人になる注意点
|
これから任意後見人の依頼を受けようか迷っている方も、ぜひ目を通してみてください。
委任者と年齢が近い人は契約を実行できない可能性がある
配偶者などで任意後見人として受任する人の年齢がご本人と近い場合、いざ任意後見制度を利用したいタイミングに、同じく認知能力に問題が出てくる可能性があります。
また、任意後見人が先に亡くなるなどのリスクが高いため、できるだけ年齢が離れている方に依頼するのがおすすめです。
一度任意後見人になると基本的に辞退できない
任意後見人を引き受けると、特段の事情がない限りは辞任ができません。
例えば、「仕事が忙しくなった」「性格が合わない」などの理由では任意後見人を辞められないため、引き受ける際にはよく考える必要があります。
ただし、以下に該当する場合に「正当な理由」として家庭裁判所に許可されれば、任意後見契約の解除をもって任意後見人を辞退できます。
■任意後見人を辞退できる条件
|
ちなみに、任意後見監督人がまだ選任されておらず任意後見契約がスタートしていない状態、つまり任意後見受任者の段階でなら、ご本人または任意後見受任者のどちらかの意思で辞められます。
任意後見受任者を辞退する場合は公証役場で「合意解除公正証書」を作成し、任意後見契約を解除しましょう。
任意後見監督人への報告義務がある
任意後見人として委任者の身の回りの手続きや財産の管理などを始めたら、任意後見監督人にどのようなことを行ったかを報告する義務が発生します。
報告の際には、財産目録や報告書などの提出が求められる場合もあり、定期的に指定された期限に作成する必要があるので手間や時間が取られることは理解しておかなくてはいけません。
任意後見人は身内と第三者どちらに頼むのがいい?
任意後見人はご本人が任せたいと考える身近な人に依頼できますが、身内に委任すると迷惑をかけるのではないか、仕事と両立できなくなるのではと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
任意後見人として指名したい方とよく話し合い、相手の意思も尊重しながら契約を進めれば、双方の気持ちも確認できるため不安を減らせます。
しかし、身近な方の時間や労力を奪ってしまうのではと悩むなら、任意後見を担う専門職や法人団体に依頼するのも一つの方法です。
ただし、任意後見契約を結ぶとお金の管理や認知能力が低下した後の生活のサポートも任せるケースが出てくるため、第三者機関に依頼する場合は信頼性や実績などもしっかりと確認したうえで判断するのがおすすめです。
任意後見人を決めておけば老後の備えになります
人はだれしも年を取るので、物忘れが多くなったり、大切な契約を自分一人では決められなくなったりするのは当たり前のことです。
生涯自分らしく、安心して生活していくために、任意後見契約を任意後見人と結んでおけば、いざ認知能力が低下した時にも社会的・身体的に守られるので大きな備えとなります。
任意後見人は、家族や信頼できる方に依頼しても良いですが、サポート体制が整ったプロに依頼すれば法律面でも生活面でもトータルで支援を受けられる場合もあります。
キャストグローバルでは、任意後見制度についてのご相談や任意後見人の依頼に関するご質問も承っておりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
----------------------------------------------------------------------
司法書士法人キャストグローバル(広島事務所)
広島県広島市中区紙屋町1丁目3-2
銀泉広島ビル5階
電話番号 : 082-246-0630
FAX番号 : 082-246-0640
広島で随時無料相談を実施中
----------------------------------------------------------------------