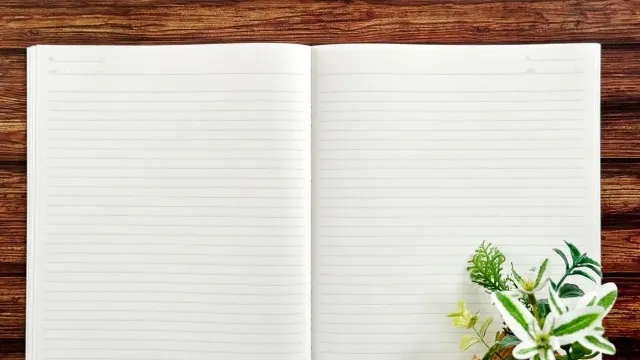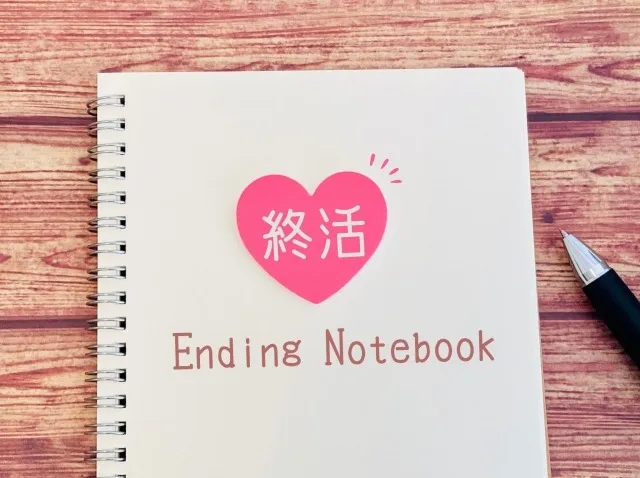遺言書の基本の書き方 相続パターン別の見本やポイントも解説
2025/03/27
終活のひとつとして遺言書を作成したいとお考えなら、正しい書き方や見本を知りたいと思われる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ご自分で遺言書を作成する際に知っておいていただきたいことや実際の書き方、パターン別の見本などを分かりやすく解説します。
遺言書のミスや不備による無効を防ぐために有効な方法も紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
遺言書の書き方や見本の前に知っておいていただきたいこと
遺言書の書き方や見本について紹介する前に、まず知っておいていただきたい4つについてお話しします。
|
|
上記を理解したうえで遺言書を作成すれば、効率良く手続きが進められるでしょう。
公正証書遺言の場合は自分で書き方や見本を調べる必要がない
遺言書には一般的なもので主に「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」の2つの種類があります。
2種類の遺言書の違いを一覧表でまとめたので、ご覧ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自筆証書遺言書は、遺言者本人が自筆かつ手書きで作成する決まりがあるため、正しい書き方や見本は調べておく必要があります。
しかし、公正証書遺言書は公証役場へ行き、遺言者本人と他2名以上の立ち会い人の下、公証人が遺言書を作成します。
業務として遺言書の作成などに携わる公証人が作成するため、遺言者本人が書き方や見本を調べておく必要はありません。
自筆証書遺言書を作成する場合は、ご自分で正しい書き方や見本を確認しておきましょう。
専門家に依頼する場合は書き方や見本の心配は不要
遺言書は、自分で内容を考えて作成する以外にも、士業の専門家に依頼して作成してもらうこともできます。
遺言書の内容は、相続人の数や財産によって複雑になったり、書き方によっては相続方法として認められなかったりする恐れがあります。
自筆証書遺言書を選ぶとしても内容は専門家に作成してもらい、決定したものを自筆で紙に手書きすれば問題ありません。
専門家に依頼する場合は、遺言書に不備やミスがないよう書き方や様式などのサポートも行ってもらえるため、自分で調べておく必要はないでしょう。
遺留分に注意して遺言書を作成する
遺言書は、遺言を残す方の意思を反映させるうえでもっとも有効な方法として、法定相続分や相続人同士の話し合いよりも優先されます。
ただし、遺言書を残しても遺言者の意思が100%通るわけではなく、法定相続人の遺留分を侵害した内容で遺言を残すとトラブルになる可能性があります。
ご自身の死後に残された家族や親族で揉め事が起こらないよう、遺留分についても留意しながら遺言書を作成するのがおすすめです。
|
|
死後の手続きなどは遺言書に記載しても法的効力を持たない
遺言書は、遺産を誰にどのように分けるのか指定できるものであって、お金に関すること以外は記載しても法定効力を持たず、亡くなった後に執行してもらえない可能性があります。
たとえば、ご自分の葬儀やお墓に関する希望、SNSのアカウントや財産には含まれない遺品の処分、飼っているペットの世話などは遺言書ではなく、別途「死後事務委任契約」を結んでおくと良いでしょう。
死後事務委任契約については、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
|
|
自筆証書遺言書【基本の書き方・見本】
ご自分で自筆証書遺言書を作成する場合、基本の書き方は以下のとおりです。
|
自筆証書遺言書の紙やペンについては特に決まりがありませんが、後ほど解説する「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は以下の様式を守りましょう。
|
|
法務省のホームページには自筆証書遺言書の見本が掲載されているので、参考にするのもおすすめです。
引用:遺言書の様式等についての注意事項|自筆証書遺言書保管制度
遺言者本人が全文や作成年月日を自筆で記載する
自筆証書遺言書は、遺言を残す方が自分で全文を紙に記載する必要があります。
パソコンやスマホなどで入力した文章は、正式な遺言書として認められないので、ご注意ください。
また、作成した年月日も正しく詳細に記載しておかなければ遺言書が無効となるので、漏れなく記載します。
住民票の記載通りに署名し、押印する
遺言の内容を記載したら、遺言者の氏名を住民票に記載されている通りに記載し、押印しましょう。
また、遺言書に相続人や遺贈者として記載する方の氏名や生年月日も住民票に記載されているものと同じでないといけません。
印鑑は認印などでも問題ありませんが、シャチハタ印などのスタンプで押すタイプは避けましょう。
遺言執行者を記載する
遺言書には、ご自分が亡くなった後に遺言を執行してくれる人を指名して、記載するのがおすすめです。
遺言執行者の記載は、必ずしも必要ではありませんが、指定しておくと死去後に法定相続人間での手続きや遺産の分配がスムーズになります。
訂正部分には二重線と訂正印を押し、変更した旨の記載と署名をする
もし、自筆証書遺言書の記載に訂正や書き直しが必要になった時は、修正ペンなどで訂正部分を消すと無効になります。
訂正が必要な個所には二重線を引いて、訂正印を押しましょう。
また、遺言書の下部などに訂正をした旨記載をして、遺言者の署名をする必要があります。
添付する財産目録は自筆でなくてもOK
遺産として不動産や株式などが複数あったり、遺言書にすべて書くと複雑になったりする場合は、財産目録を添付します。
自筆証書遺言書はパソコンなどで作成できませんが、財産目録に関しては自筆以外でも問題ありません。
また、住所や家屋番号などが分かる登記事項証明書のコピーや銀行名・支店名・口座名義・口座番号がわかる通帳のコピーを添付することでも財産目録の代わりになります。
ただし、自筆以外で財産目録を作成する場合も全てのページに総ページ数が分かるよう通し番号を入れ、署名と押印も必要です。
遺言書のパターン別書き方・見本
遺言書を作成したい方は、誰にどの遺産をどのような配分で渡すのかが重要だとお考えではないでしょうか。
誰に遺産をどのように分配するかによって遺言書の書き方も異なるため、パターン別に見本を紹介します。
【配偶者がすべて相続】遺言書の書き方・見本
まずは子どもがいないご夫婦で、配偶者に遺産のすべてを相続させたい場合の遺言書の書き方と見本です。
遺言書内に、配偶者の氏名と生年月日を書き、すべての財産を相続させたい旨記載します。
ただし、亡くなった方の親が存命の場合は、法律で定められた遺留分があるので、遺言書の作成前に遺言の内容について相談しておくのがおすすめです。
【配偶者と子どもで相続】遺言書の書き方・見本
配偶者と子どもで遺産を相続させる上で、配分や財産の指定がある場合の遺言書の書き方と見本です。
配偶者と子どもで遺産を相続する場合、遺言書がなければ法定相続分として配偶者が1/2、子どもが1/2で分配します。
遺産を個別に指定して相続させたい時に、遺言書を残しておくと希望が伝わるのでおすすめです。
遺言執行者を遺言者と同世代の配偶者に指定する場合は、万が一先に亡くなってしまった時のために子どもの氏名も記載しておくと安心です。
【子どもがすべて相続】遺言書の書き方・見本
亡くなった方に配偶者がおらず、子どもがすべて遺産を相続する場合は法定相続分で分けると均等に人数で分配されます。
もし、子どものうち1人が特に世話をしてくれたなどの理由で遺産の割合に差をつけたいのであれば遺言書に記載しておくといいでしょう。
ただし、子どものみで遺産を分配する場合の遺留分は、例えば子どもが3人なら1人あたり全体の1/6となるので侵害しないよう注意が必要です。
また、遺言書には「付言事項」として遺族へのメッセージを記載できます。
法的効力はありませんが、残された家族のために一筆記しておくと想いが伝えられて遺産の分配もスムーズに行える場合があります。
【法定相続人以外が相続】遺言書の書き方・見本
法定相続人として定められた家族や親族以外の人、例えば内縁の妻や良くしてくれた友人などに遺産を分配したい場合も遺言書が有効になります。
法定相続人以外に遺産を分ける場合の書き方と見本は、以下を参考にしてみてください。
法定相続人以外に遺産を分配する場合は、「遺贈」と記載する必要があります。
他に法定相続人がいる場合は遺留分などに留意し、生前贈与しておいたり付言事項を記しておいたりと、亡くなった後にトラブルとならないよう配慮しましょう。
【団体などに遺産を寄付】遺言書の書き方・見本
ご自分の財産を団体などに寄付したいとお考えなら、以下の遺言書の書き方や見本を参考に作成してみましょう。
遺産を団体に遺贈する場合は、ご自身の死後に代わりに寄付の手続きをしてくれる遺言執行者を指定しておくといいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用するのもおすすめ
自分で遺言書を作成する場合、書き方や署名・押印、日付などに不備があれば内容が認められない可能性があります。
せっかく作成した遺言書が亡くなった後に無効とならないよう、「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめです。
自筆証書遺言書保管制度は、作成した遺言書を法務局に持ち込んで遺言書保管申請を行い、遺言書保管所に原本と画像データを保管してもらうものです。
引用:知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方|政府広報オンライン
遺言書の紛失や第三者による改ざんを防げるほか、署名や押印、日付の記載など遺言書として不備とされるミスがあれば受け取りを拒否されるので、一定のチェックができます。
ただし、遺言書の内容や相続の方法などについての相談はできないので、不安がある場合は専門家に確認を依頼すると無難です。
遺言書の書き方や見本はまずプロに相談してみましょう
遺言書を作成する場合、公正証書遺言書を残すのであればご自分で書き方や見本を確認する必要はありません。
自筆証書遺言書を作成する場合は、本記事で紹介した書き方や見本、様式などを守らなければ無効になる可能性もあります。
遺言書を作成するのであれば、有効性を高めるためにまずは相続のプロに相談してみるのがおすすめです。
キャストグローバルでは遺言書作成や相続内容に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
----------------------------------------------------------------------
司法書士法人キャストグローバル(広島事務所)
広島県広島市中区紙屋町1丁目3-2
銀泉広島ビル5階
電話番号 : 082-246-0630
FAX番号 : 082-246-0640
広島で正確な遺言書作成を支援
広島で随時無料相談を実施中
----------------------------------------------------------------------